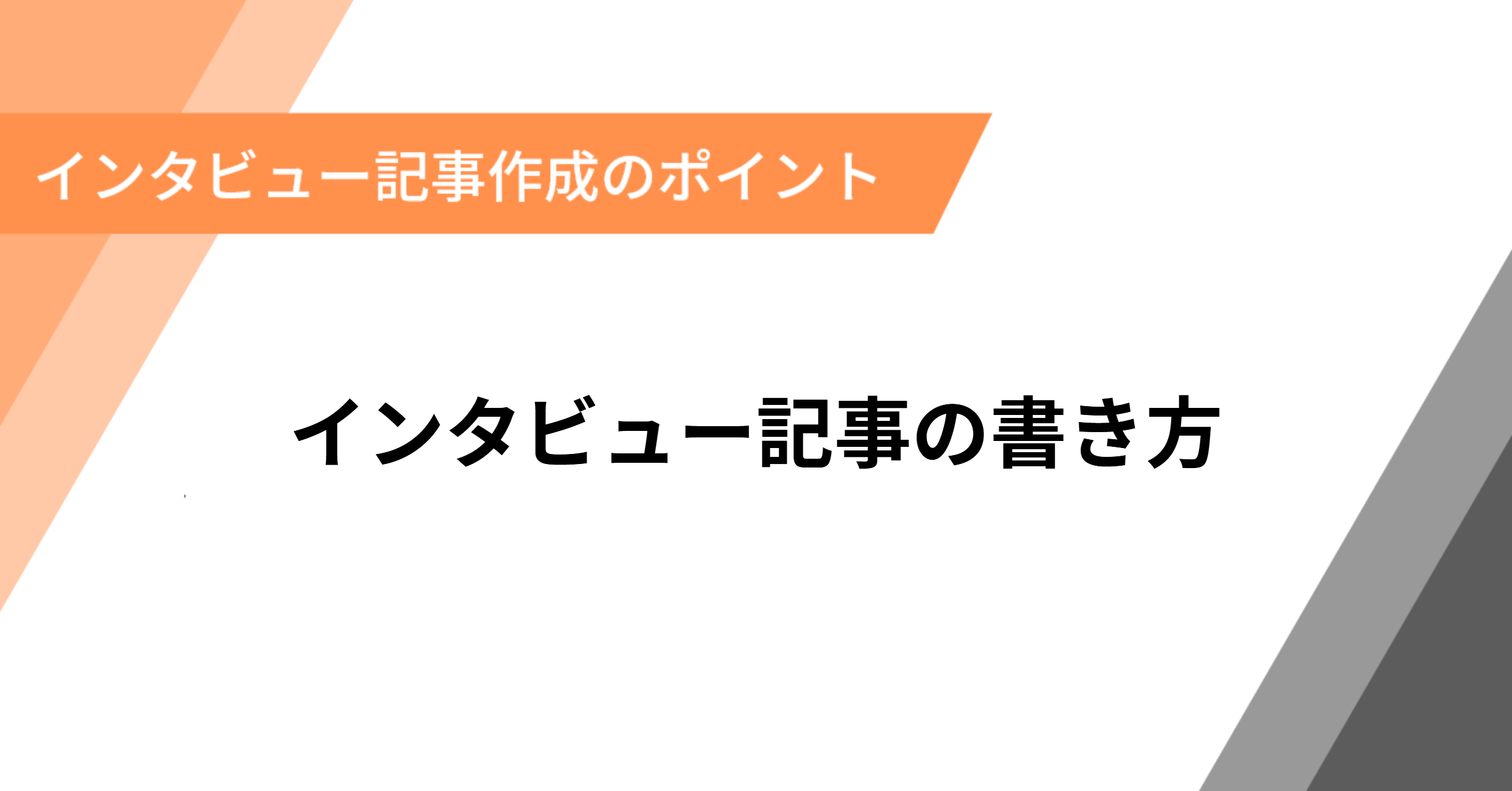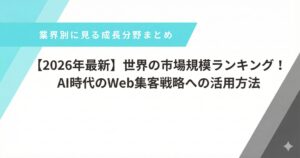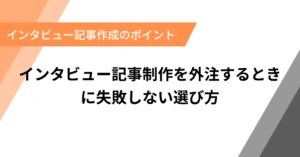はじめに

インタビュー記事は、ただ話を聞いてまとめるだけのものではありません。語り手の背景や考え方を丁寧に掘り下げ、読者に伝わる形で再構成していくことが求められます。そこに編集者の解釈や構成力が加わることで、単なる記録ではなく、読者が“人を感じる記事”へと変わります。
この記事では、インタビューの中でも特に「執筆・記事化」に焦点を当て、準備から構成、語り口、仕上げまでを実践的に解説します。初心者から中級者の方までが、自信を持って記事を形にできるようになることを目的としています。
インタビュー記事全体の書き方・ 流れについては以下の記事でご紹介しています。
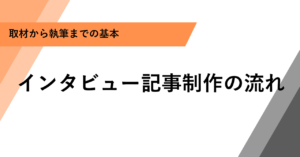
取材・インタビュー記事の“書く工程”とは
インタビュー記事の執筆は、単に取材内容を書き起こす作業ではありません。
語り手の考えや背景を整理し、読者が自然に理解できる形へと再構成していくプロセスです。どんなに内容が深くても、企画の意図が曖昧なままでは伝わりません。
まず大切なのは、**「なぜこの人に話を聞いたのか」「誰に届けたいのか」**という意図を明確にすることです。これが執筆の軸になります。取材現場では想定外の話題が出ることもありますが、それを無理に排除する必要はありません。むしろ、その人らしさを表す“発見”として捉え、構成にどう活かすかを考えることが大切です。
記事化の工程では、事前に立てた構成と、取材で得た発見を行き来しながら物語を組み立てることがポイントです。ニュース記事やSEO記事が情報整理を目的とするのに対し、インタビュー記事は「語り手の世界を読者に感じてもらう」ことが目的になります。
そのために意識すべき3つの視点は次の通りです。
- 意図を理解する — 取材目的をはっきりさせ、構成の中心を定める。
- 語り手を尊重する — 言葉を整えすぎず、話し方の温度を残す。
- 読者を導く — 読みやすい順に並べ、理解しやすい流れに整える。
この3点を押さえるだけで、文章の方向性がぶれなくなります。
インタビューの魅力は、語り手の言葉と編集の意図が重なったときに初めて生まれるのです。
文字起こしから構成を作る
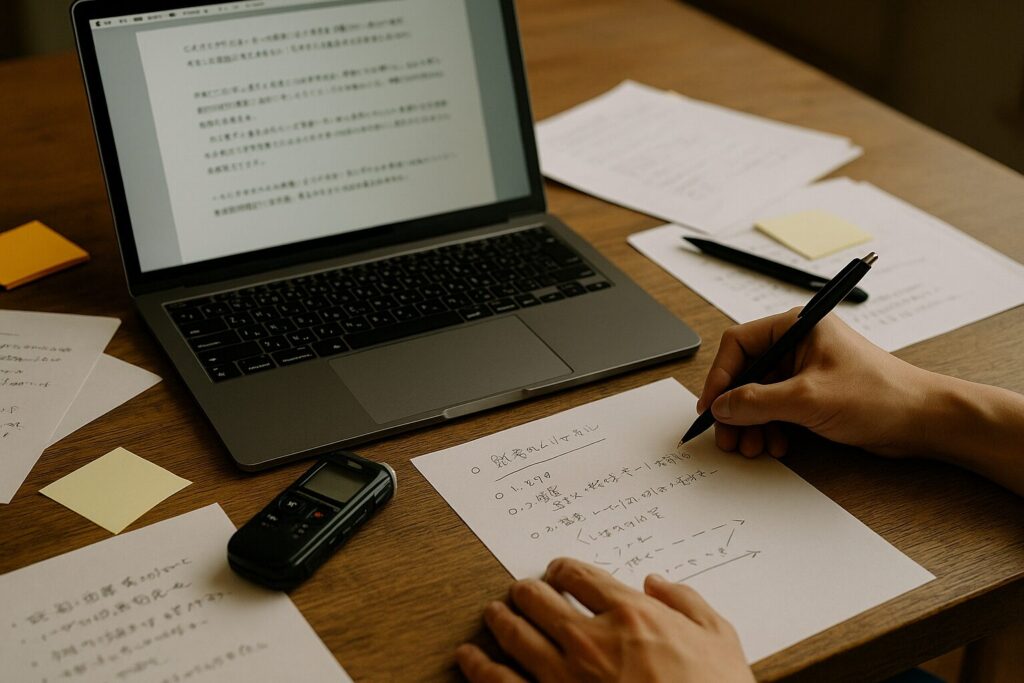
取材を終えたあとの第一歩が、文字起こしです。
ここでは、録音データを文字にするだけでなく、「素材をどう整理し、構成に落とし込むか」がポイントになります。単に話した順に並べても、読者にとってわかりやすい記事にはなりません。
まずは、すべての発言を時系列で確認しながら、どの部分に「テーマの核」や「印象的なエピソード」があるかをチェックします。その上で、内容を話題ごとに分類し、関連する発言をグループ化していきます。ここで重要なのは、「語り手が話した順」と「読者が理解しやすい順」は違う、という点です。
取材前に立てた構成案と照らし合わせながら、流れがずれている場合は、新しい発見として構成を再設計します。構成とは、語り手の思考を編集者の論理で翻訳する設計図のようなものです。
整理が進んだら、次の3つの軸で見直してみましょう。
- 時系列 — いつ・どのような流れで起きた話なのか。
- テーマ — どんな課題・視点・価値観を中心に話しているか。
- 成果・示唆 — そこから読者が何を学べるか。
この3軸を行き来することで、話の全体像が整理され、章立て(H2・H3)が自然に浮かび上がります。
構成を作る段階で、すでに「記事の読みやすさ」は8割決まるとも言われます。
素材を“並べる”ではなく、“意味でつなぐ”意識を持つことが、インタビュー執筆の第一歩です。
リード文の書き方
リード文は、インタビュー記事の印象を決める最初のパートです。
どんなに内容が良くても、導入で読者の関心をつかめなければ記事は読まれません。リードは単なる「前置き」ではなく、「なぜこの記事を読むべきか」を示す役割を持っています。
まず意識すべきは、“誰が・なぜ・何を語るのか”を一文で伝えることです。
この3点が明確になっていると、読者は安心して本文に進めます。反対に、導入が抽象的だと、途中で離脱されることが多くなります。
リード作成の基本手順
読者にとっての“読む理由”を添える
「この話を知ることでどんな気づきが得られるか」を端的に伝えます。
取材のテーマを一言でまとめる
そのインタビューで最も伝えたいメッセージを、一文で書き出します。
語り手の立場と背景を明示する
人物紹介は最小限に。記事の文脈上必要な情報だけに絞ります。
例:
株式会社ストリクトワークス代表の田中さん。スタートアップから大手企業まで、組織改革を支援してきた同氏に「リモート時代の信頼構築」について伺いました。
シリーズ連載や企業メディアなど、複数のインタビューを並行して掲載する場合は、リードのフォーマットを一定に保つことも効果的です。構成を揃えることで読者が迷わず、メディア全体の統一感が生まれます。
リード文は“記事の顔”です。
人物紹介ではなく、「物語の入口」として設計しましょう。読む理由をきちんと提示できれば、記事全体の方向性が自然に定まります。
本文構成(基本の型)

インタビュー記事の本文は、素材をどう並べるかで読みやすさが大きく変わります。
同じ内容でも、順序や切り口が異なるだけで印象がまったく違って見えるものです。
読者が理解しやすい流れを設計することが、本文構成の第一歩になります。
まず意識したいのは、取材時の話の順番=記事の順番ではないという点です。
語り手の言葉をそのまま並べると、取材の臨場感は残りますが、読者にとっては流れが掴みにくくなることがあります。
そのため、執筆段階では「読者がどう理解していくか」を軸に再構成することが大切です。
構成の基本型
- 時系列型:過去から現在へと変化を描く
- テーマ型:話題ごとに整理して掘り下げる
- ハイブリッド型:時間とテーマを交差させ、物語性と整理性を両立する
H2(大見出し)は読者の関心に沿う問いかけ形式にし、H3(小見出し)では具体的なエピソードを展開すると読みやすくなります。
H2:信頼がチームを動かした
H3:リモート初期の混乱
H3:“共有”を軸にした文化形成
章立てを作るときは、「話題を分ける」よりも「理解を導く」視点で構成することが大切です。
読者がスムーズに流れを追えるように、ひとつの章ごとに「問いと答え」が見える構成を目指しましょう。
トーンと語り口の選び方
インタビュー記事は、語り手の個性をどう文章に残すかで印象が大きく変わります。
同じ内容でも、語り口の選び方ひとつで、伝わり方や温度感がまったく違うものになるからです。
「整えること」と「残すこと」のバランスを取るのが、ライターの腕の見せどころです。
インタビュー記事でよく使われる文体は、大きく3種類あります。
| 文体 | 特徴 | 向いている記事 |
|---|---|---|
| 三人称(〜と語る) | 客観的で整理された印象。事実関係を明確に伝えやすい。 | BtoB、採用広報系、ビジネス媒体など |
| 一人称(“〜だと思います”) | 温度感や人柄が伝わりやすい。読者との距離が近い。 | カルチャー記事、人物特集、ブランド系媒体 |
| 混合型 | 客観と主観のバランスが良く、テンポが生まれやすい。 | 一般的なインタビュー媒体、企業ブログなど |
文体を選ぶ際は、**「誰に読ませたいか」「どんな印象を残したいか」**を基準にします。
企業メディアでは信頼性を優先して三人称が多く、読者との距離を近づけたい記事では一人称を残すことが多いです。
発言を整えるときのポイントは、意味を変えずに読みやすくすることです。
文法を直したり言い回しを簡潔にすることは構いませんが、言葉のトーンまで変えてしまうと語り手の“声”が消えてしまいます。
口語を少し残すだけでも、その人らしさがぐっと生きてきます。
例:
「いや〜、ほんとにバタバタで(笑)」
→ 「当時は本当に手探りの状態でした」と書き換えることで、印象は変わりますが、熱量も少し失われます。どちらを採るかは記事の目的次第です。
整えすぎない、残しすぎない。
このバランスが保たれている記事ほど、読者に「人」を感じさせます。
文体を意識することは、単なる書き方の問題ではなく、記事全体の印象をデザインする作業なのです。
引用と注釈の扱い方
インタビュー記事において、引用は語り手の言葉を生かし、記事にリアリティを与える大切な要素です。
読者は「その人が実際に話した言葉」から、感情や価値観を感じ取ります。
一方で、引用を多用しすぎるとテンポが悪くなったり、情報が散らかった印象になることもあります。
引用と編集文のバランスをとることが、記事全体の読みやすさを左右します。
引用部分は、発言の意図を変えずに整理するのが基本です。
言葉遣いを整えたり、文末を統一することは問題ありません。
ただし、語彙を置き換えたり、文脈を省略しすぎると意味が変わってしまうので注意が必要です。
「整える」と「書き換える」は違う、という意識を常に持ちましょう。
良い引用の基本ルール
- 要点を選ぶ — すべてを残すのではなく、話の流れを支える部分を抽出する。
- 長さを調整する — 長文になりすぎた場合は要約でつなぐ。
- 前後を補う — 読者が理解できるように、編集者の一文で文脈を補足する。
例:
編集前:「いや〜、ほんとにバタバタで(笑)。なんか方向性も決まってなくて…」
編集後:「最初は方向性も定まらず、手探りの状態でした。その中で“信頼関係をどう築くか”が一番の課題だったと思います。」
このように、意味を保ったまま整えることで、読みやすさと誠実さの両立ができます。
また、専門用語や略称には軽い注釈(脚注・括弧)を加えると親切です。
ただし、注釈が多すぎると読者の集中が途切れるため、最小限に留めましょう。
記事の中で理解しづらい用語は、最初の登場時に一度だけ簡潔に説明するのが理想です。
引用の目的は“発言をそのまま見せること”ではなく、“言葉を通して人を伝えること”です。
語り手の声を活かしながら、読者が無理なく読み進められるリズムを整えることを意識しましょう。
素材と構成をもとに記事化する

取材と構成の準備が整ったら、いよいよ記事化の段階に入ります。
記事化とは、素材を再整理し、構成に沿って“読者に伝わる順序”で言葉を組み立てる工程です。
ここでの目的は、素材をすべて詰め込むことではなく、意図と流れを持った「語りの設計」をすることにあります。
記事化の全体の流れ
- 素材を整理する
- 取材メモや文字起こしを構成の章立て(H2ごと)に分類
- 使いたい引用をマーキングし、不要な部分は思い切って除外
- 一覧化(スプレッドシートやNotionなど)で視覚的に確認
- 章ごとに“伝えたい1文”を決める
- 各章に「この章で伝えるメッセージ」を一文で書き出す
- たとえば:「この章では“転機と成長”を描く」「この章では“価値観の変化”を見せる」など
- これが文体・引用・構成の軸になります
- 素材を並べて流れを作る
- 発言を章の流れに合わせて並べ替え
- 会話順ではなく、読者が理解しやすい順に整理
- 発言の間には編集者の“つなぎ文”を挟む 例:「こうした経験を経て、佐藤さんは次のように語ります。」
- 引用と地の文のバランスを調整する
- 引用が多くなるときは、地の文で要約をはさむ
- 要約 → 引用 → 補足、のリズムを意識する
- 編集文は“説明”ではなく、“導線”として機能させる
- トーンを整える
- 文末や語調を統一し、全体のリズムを確認
- 口語が強い箇所は残すかどうかを意図に沿って判断
- リードと結びを見直す
- 本文を書き終えた後に、導入と締めを調整
- 「読後感」と「冒頭の印象」が一致するように修正する
記事化のポイント
- 素材を“構成に合わせる”のではなく、“読者に合わせて再設計する”
- 発言の順序よりも理解の順序を優先する
- 語り手の意図を守りながら、読者の読みやすさをつくる
作業時のコツ
- 最初は「素材をすべて並べる」つもりでラフを作る
- 一度書き上げてから、不要な部分を削る(引き算の編集)
- 文章全体を声に出して読んでみると、リズムの偏りを発見しやすい
- 各章の最初と最後の文をつなげて読んでみると、構成の流れが明確に見える
記事化とは、素材を文章に置き換えることではなく、「人の語りを物語に変換する」プロセスです。
語り手の思考と読者の理解が交わるように再構成できれば、インタビューは記録から作品へと変わります。
付録:ツールとワークフロー
インタビュー記事制作は、創造性だけでなく再現性のある工程設計が大切です。各段階で使えるツールを整備しておくと、作業効率が大きく変わります。
| フェーズ | 内容 | 推奨ツール |
|---|---|---|
| ① 取材準備 | 目的・質問整理 | Google Docs/Notion |
| ② 録音・取材 | 音声収録・写真撮影 | Zoom/Voice Recorder/Notta |
| ③ 文字起こし | テキスト化・タグ付け | Whisper/Otter.ai/Notion |
| ④ 構成・執筆 | 原稿作成・見出し設計 | Google Docs/Scrivener |
| ⑤ 校正・公開 | チェック・入稿 | Google Docs コメント機能/WordPress |
録音・原稿・構成を一つのドキュメントにまとめることで、全体の流れを保ちやすくなります。原稿確認時は修正範囲(事実確認など)を明示して依頼しましょう。公開後は更新履歴を残し、関連記事やSNS展開で継続的に活用します。
まとめ:伝わるインタビュー記事を書くために
インタビュー記事の執筆は、取材で得た言葉を「伝わる形」に変えていく編集の仕事です。
それは、情報を整理するだけではなく、語り手の思考や感情を読者に届ける“翻訳”のような行為でもあります。
良い記事とは、読者が“話している人の存在”を感じられる記事です。
そのためには、
- 目的と意図を明確にすること
- 語り手の声を尊重しながら、読者が理解できる構成に整えること
- 発言を活かしつつ、編集者の視点で流れを設計すること
この3つを常に意識することが大切です。
インタビュー執筆は、準備・構成・執筆・記事化というステップの積み重ねですが、
最も重要なのは「誰のために書くか」を見失わないことです。
読者がその言葉を読んで何を感じ、どんな気づきを得るか——
そこに意識を向けることで、文章は自然と人の心に届くものになります。
取材で得た素材の中には、必ず「その人にしか語れない一文」があります。
それをどう拾い上げ、どう届けるかがライターの力量です。
語り手の思いをすくい上げ、読者に届く形で伝える。
それが、インタビュー記事を書くということの本質なのです。
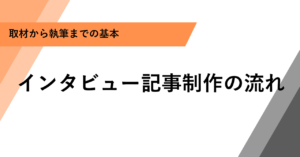
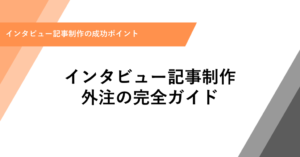
インタビュー記事制作の実績
これまでに数百件のインタビュー取材・記事化を経験。独自の「質問設計プロセス」と深掘り手法で、読み手に伝わるストーリーを構築します。
インタビュー記事制作に関するお悩みはSTSデジタルが解決します。