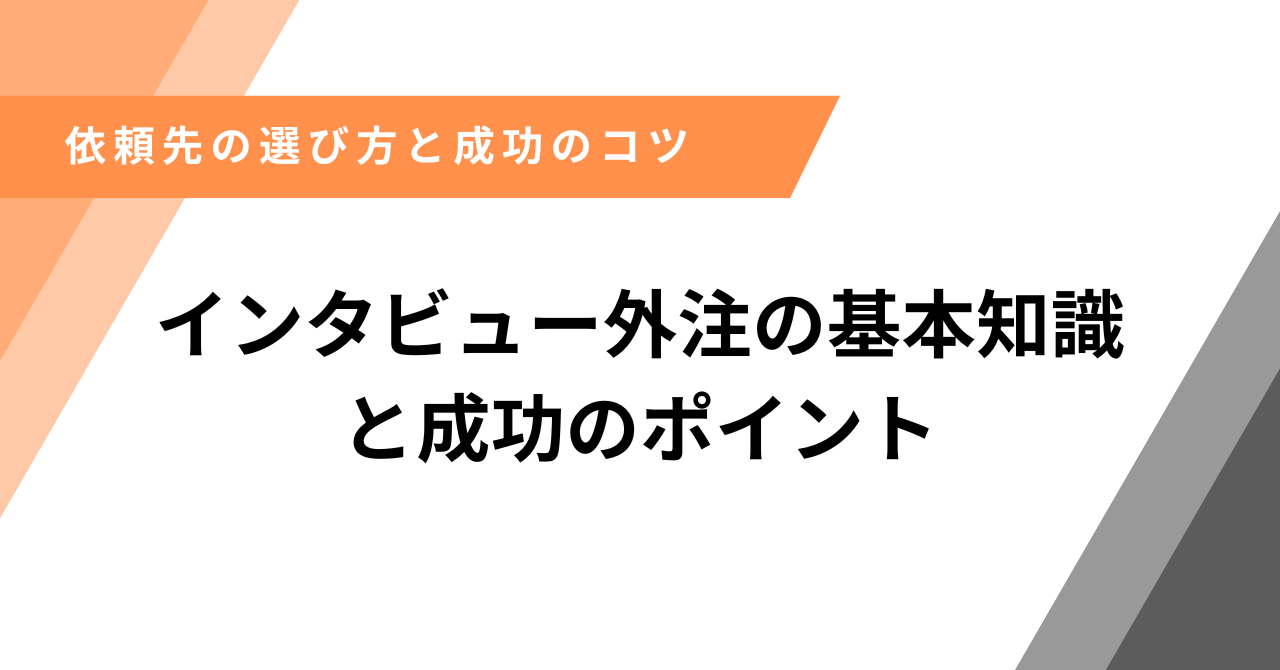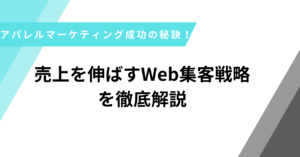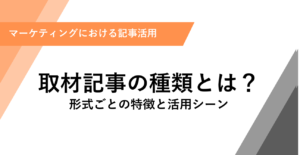インタビュー記事を外注したいけれど、「どこに頼めばいい?」「費用は?」「失敗しないコツは?」と悩む方は多いでしょう。
この記事では、インタビュー外注の基本から実践の流れ、注意点、そして成功事例までを、図表を交えて分かりやすく解説します。
1. インタビュー外注とは
インタビュー外注とは、企業や個人が取材やインタビューの実施・執筆・編集を外部の専門家に委託することを指します。
採用広報や導入事例制作、広報・PRコンテンツなど、幅広いシーンで活用されています。
外注を利用する主な目的
- 社内リソースの不足を補う
- 専門的な取材・編集スキルを取り入れる
- 客観的な視点からブランドの魅力を引き出す
💡 補足:
特にBtoB企業では、技術理解とストーリーテリングを両立できる外部ライターへの依頼が増えています。
2. 外注のメリットとデメリット
外注には大きな利点がある一方で、注意すべき点も存在します。
以下に、主なポイントを表にまとめます。
| 観点 | メリット | デメリット |
| 品質 | プロによる構成・執筆で内容が洗練される | 自社トーンとズレる場合がある |
| 工数 | 社内の時間を節約できる | 打ち合わせや確認に時間を要する |
| コスト | 短期的には外注費で効率UP | 依頼頻度が多いと費用がかさむ |
| 視点 | 第三者の目で新しい切り口が得られる | 社内理解が浅いと意図が伝わりにくい |
結論:
外注のメリットを最大化するには、初回の目的共有と認識合わせが何より重要です。
3. インタビュー外注の流れと手順
インタビューを外注する際は、次のようなステップを踏みます。
図:インタビュー外注の流れ
目的設定 → 外注先選定 → 契約 → 取材準備 → 取材実施 → 原稿確認 → 公開
各ステップのポイント
- 目的設定
「誰に何を伝えるか」「何の成果を目指すか(CV・応募・認知)」を整理します。 - 外注先選定
業界理解、対応範囲、実績を比較します。相見積もりを取るのも有効です。 - 契約と準備
契約書で著作権・修正範囲を明記し、取材対象者・質問案を共有します。 - 取材・執筆・納品
オンライン取材が主流。初稿→修正→校了の流れを明確にスケジューリングしましょう。 - 効果測定
公開後はPV・滞在時間だけでなく、商談化・応募数・ブランド想起など実質的指標を追います。
4. 外注先の選び方
文章だけでなく「比較視点」が重要です。
以下の表と箇条書きで、選び方の基準をまとめます。
| 評価軸 | 確認すべきポイント |
|---|---|
| 専門性 | 業界やテーマに精通しているか(BtoB/医療/教育など) |
| 実績 | 過去のクライアント事例・制作物の質 |
| 対応範囲 | 企画・撮影・編集・CMS投稿まで一貫対応可能か |
| コミュニケーション | レスポンス速度・提案内容の具体性 |
| コスト | 単価と品質のバランス、修正対応の柔軟さ |
選定時のチェックリスト:
- ✅ サンプル記事を見せてもらう
- ✅ 担当ライターの経歴を確認する
✅ 納期と修正ルールを事前に決める - ✅ 契約にNDAを含める
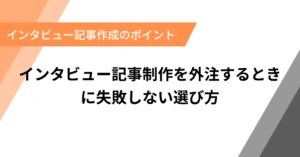
5. 契約・進行時の注意点
外注契約でのトラブルは「曖昧な取り決め」から生まれます。
特に以下の3点は、契約書に明記しておくべきです。
- 著作権と二次利用の扱い(誰が権利を持つか)
- 修正回数と納期変更ルール
- 支払い条件・キャンセルポリシー
💬 コツ: 進行中は定期的に進捗を共有し、初稿レビュー時に「構成」「トーン」「事実確認」の3軸でチェックすると安定します。
6. 費用相場の目安
外注費は依頼範囲によって変動します。以下は一般的な目安です。
| 項目 | 内容 | 相場(税抜) |
|---|---|---|
| 取材+執筆(1時間取材) | インタビュー記事1本 | 5〜15万円 |
| 編集・構成のみ | 既存記事の編集・整備 | 2〜5万円 |
| 撮影オプション | 写真撮影・レタッチ含む | 3〜6万円 |
| フルパッケージ | 企画〜撮影〜執筆〜CMS入稿 | 15〜30万円 |
※依頼先が個人ライターか制作会社かによっても変動します。
7. 成功事例から学ぶポイント
事例①:BtoB企業の導入事例記事
外部ライターが経営層にインタビューし、課題→導入→成果の流れで構成。
結果、商談化率が1.8倍に上昇しました。
事例②:採用広報インタビュー
社員のリアルな声をストーリー化。応募者の質が改善し、応募率が20%アップ。
学び
成功企業は「目的設計→事前共有→レビュー体制→継続改善」の4段階を徹底しています。
8. まとめと今後の展望
インタビュー外注の鍵は、目的と期待値の共有です。
初回は密に、2回目以降はテンプレート化して効率化することで、安定的に高品質な記事制作が可能になります。
また、AIによる書き起こし・構成支援の精度が上がりつつあり、外注の生産性も今後さらに向上します。
外注をコストではなく編集資産への投資と捉え、自社の発信力を継続的に磨きましょう。
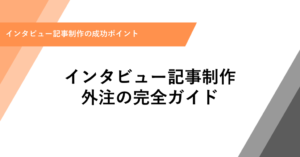
インタビュー記事制作の実績
これまでに数百件のインタビュー取材・記事化を経験。独自の「質問設計プロセス」と深掘り手法で、読み手に伝わるストーリーを構築します。
インタビュー記事制作に関するお悩みはSTSデジタルが解決します。