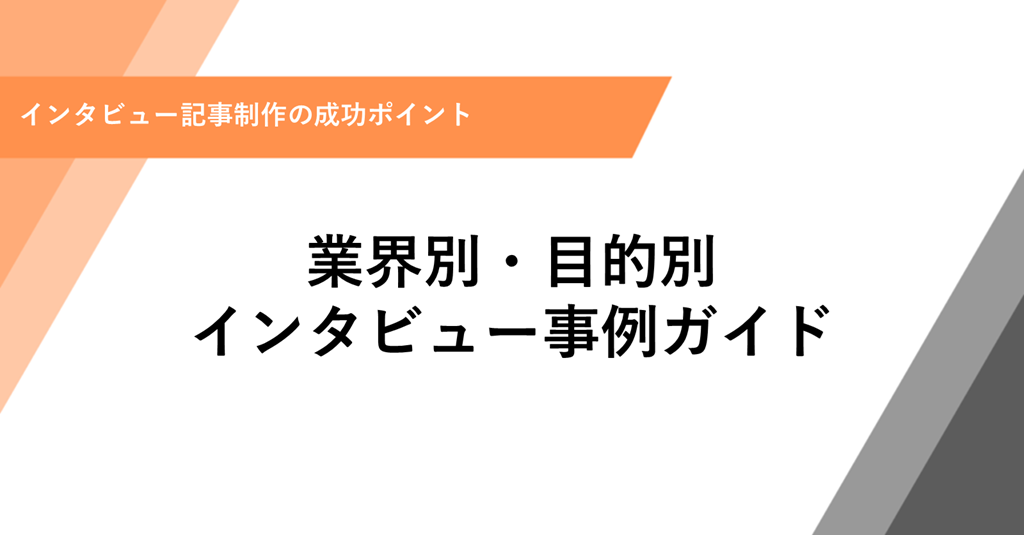インタビュー記事の効果は、どの業界で、どんな目的で制作するかによって大きく変わります。
採用広報であれば「人の魅力」や「カルチャー」を伝える構成が求められ、BtoBの導入事例なら「成果と信頼性」を明確に示す必要があります。
しかし、発注時点で「どの形式を選ぶべきか」を誤ると、せっかくの取材が目的に合わない記事になってしまいます。
ここでは、代表的な業界・目的別のインタビュー事例と、それぞれで効果を出すための構成・撮影・トーン設計のポイントを整理します。
目次
業界別インタビューの特徴とポイント
| 業界 | 主な目的 | 構成の方向性 | トーン&スタイル | 成功のポイント |
|---|---|---|---|---|
| BtoBサービス(SaaS・製造・IT) | 導入事例・信頼構築 | 課題 → 解決策 → 成果の3段構成 | 論理的・客観的 | 実数・データを交えた成果提示 |
| 採用・人事広報 | 社員の人柄・カルチャー訴求 | 入社動機 → 業務内容 → 成長実感 | 親近感・人間味重視 | 表情やオフィス写真で雰囲気を伝える |
| ブランド・広報 | 経営者・開発者の想い発信 | ストーリー中心構成 | 情緒的・誠実 | メッセージの一貫性を重視 |
| 教育・医療・公共 | 専門性・信頼性訴求 | 実践例+現場の声 | 専門用語を丁寧に説明 | 監修者・立場を明示して信頼性を担保 |
| 小売・EC・D2C | 商品・顧客体験紹介 | 商品開発背景+ユーザー声 | カジュアル・視覚重視 | 写真・動画を活用しSNS転用可能に |
目的別のインタビュー設計
インタビューの「目的」を誤ると、どんなに取材が上手くても成果は出ません。
目的ごとに、どんな構成と演出が有効かを整理します。
| 目的 | 主な読者層 | 構成例 | 成果指標(KPI) |
|---|---|---|---|
| 採用強化 | 就職・転職検討者 | 入社理由 → 現在の仕事 → 成長実感 → メッセージ | エントリー数、応募率 |
| 製品導入事例 | 見込み顧客 | 導入前の課題 → 選定理由 → 効果・数値成果 | 問い合わせ数、リード数 |
| ブランド認知 | 既存・潜在顧客 | 企業ストーリー → 使命・価値観 → 今後の展望 | PV、SNSシェア数 |
| 顧客事例(ユーザーの声) | 同業他社・見込み顧客 | 利用背景 → 使用感 → 成果・評価 | CVR・CV数 |
| 社内広報・IR | 取引先・株主 | 代表・責任者インタビュー | 信頼度・投資関心度 |
成果が出やすい構成フォーマット
目的と業界を組み合わせることで、再現性の高い構成をテンプレート化できます。
下表は実務で活用される代表的なフォーマット例です。
| フォーマット名 | 主な用途 | 構成要素 | 記事トーン |
|---|---|---|---|
| 導入事例型 | SaaS・製造・BtoB | 課題 → 解決策 → 効果 → 今後の展望 | 実績・信頼中心 |
| 社員インタビュー型 | 採用・人事 | 入社理由 → 現在の役割 → 成長 → 社風 | 人物中心・温かみ |
| ブランドストーリー型 | 広報・経営層発信 | 会社理念 → 創業経緯 → 今後の挑戦 | 誠実・理念訴求 |
| 共同プロジェクト型 | 開発・研究・自治体 | 背景 → 連携経緯 → 成果 → 将来像 | 中立・専門性重視 |
写真・映像演出のポイント
インタビュー記事では、文字情報だけでなくビジュアルの設計が重要です。
発信目的に合わせて、どのような撮影素材を組み合わせるかを事前に設計します。
撮影・素材構成の基本例
- BtoB事例:製品利用シーン・チーム会議・操作画面などを含める
- 採用記事:社員の自然な表情、オフィス環境、チーム風景
- ブランドインタビュー:経営者のポートレート、オフィス背景、ロゴ入りカット
- 教育・医療:現場設備、指導風景、使用中のツール
撮影依頼時のチェックポイント
- カメラマンへのブリーフを外注前に共有
- 撮影禁止・注意箇所を明確化
- 掲載形式(横長/縦長/SNS転用)を事前指定
成功事例:業界別インタビューの活用パターン
| 業界 | 成功の型 | ポイント |
|---|---|---|
| SaaS企業 | 導入企業の業務改善を数値で見せる | Before→Afterの構成を明示 |
| 採用広報 | 複数職種インタビューをシリーズ化 | 同一トーンで継続的発信 |
| EC・D2C | 商品開発者×ユーザー対談形式 | 双方向の熱量を表現 |
| 教育・NPO | 学習者や支援対象者の声を中心に構成 | エモーショナル+社会的意義を強調 |
まとめ
インタビュー記事を成果につなげるには、業界と目的の両面で「設計意図」を持つことが欠かせません。
記事フォーマットを選ぶ段階で、
- 何を伝えたいか(目的)
- 誰に読ませたいか(読者)
- どの印象を残したいか(トーン・構成)
この3点を明確にしておけば、外注制作でもブレないコンテンツが作れます。
あわせて読みたい

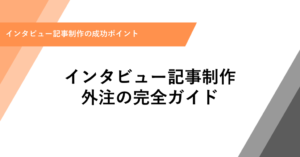
インタビュー記事制作・外注の完全ガイド
取材から撮影、ライティングまで ― 成功する外注設計をすべて解説 企業の広報やマーケティング、採用活動で「インタビュー記事を制作したい」と考えたとき、最初に直面…
インタビュー記事制作の実績
これまでに数百件のインタビュー取材・記事化を経験。独自の「質問設計プロセス」と深掘り手法で、読み手に伝わるストーリーを構築します。
インタビュー記事制作に関するお悩みはSTSデジタルが解決します。